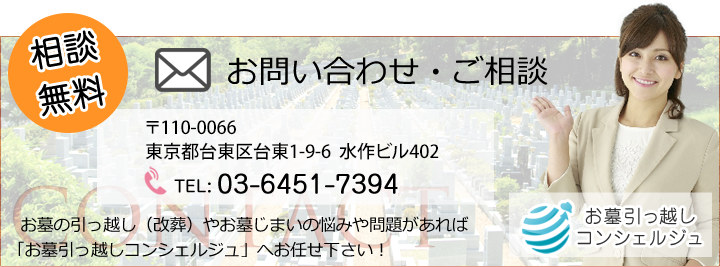伝燈院 赤坂浄苑 (でんとういん あかさかじょうえん)
- カテゴリ: お墓引っ越し 納骨堂
お墓引っ越しコンシェルジュです。
最近は、終活という言葉が世間に認知されてきていますが、
超高齢社会の中、相続や介護・医療などの問題はさらに深刻になってきています。
そして、実家のお墓や親戚の田舎のお墓などで様々問題が増えてきています。
お墓の承継問題や古いお墓の撤去・墓じまいなどの事例が多くなり、
様々な供養や埋葬方法が増えています。
お墓引っ越しコンシェルジュが、
供養や風習、納骨方法、日本の風習などを
難しく解説をするのではなく、解りやすい説明を致します。
少しでも納得してもらえたら幸いです。
本日は、「伝燈院 赤坂浄苑」を紹介します。
赤坂浄苑は、
カードリーダーで管理されている搬送式納骨堂となり格調高い参拝ブースとなります。
1つひとつが区切られているため、プライベートな空間で静かに故人を偲ぶことができます。
また、室内の納骨堂の特長である天候に関わらずお参りができ、夜の9時まで参拝できます。
あらかじめ生花が供えられていて、手前には焼香台もあり、
納骨堂なので草取りなどのお掃除の心配もありません。
地下鉄の赤坂見附駅から徒歩2分という好立地もオススメポイントです。
館内は完全なバリアフリー設計で、建物は安心の耐震設計です。
最新の納骨施設ですが、
事業主は、伝燈院は金沢市に本院を置く曹洞宗の寺院なのでしっかりと供養されます。
そして、宗教・宗派・国籍は問われませんので、どなたでも納骨できます。
これからも、お墓引っ越しコンシェルジュは、
改葬(お墓の引っ越し・お墓の移動・墓石の移し)・
古いお墓の撤去・墓じまいなどの相談や困り事のお手伝いを致します。
また、遺品整理やお墓参りの同行、お墓の掃除などのお手伝いも受け付けております。
今後は、様々な供養方法や納骨施設の情報などを公開していきます。
https://www.ohaka-hikkoshi-kaisou.com
2016年01月08日 21:56
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
眞應殿 しんのうでん
- カテゴリ: お墓引っ越し 納骨堂
お墓引っ越しコンシェルジュです。
最近は、終活という言葉が世間に認知されてきていますが、
超高齢社会の中、相続や介護・医療などの問題はさらに深刻になってきています。
そして、実家のお墓や親戚の田舎のお墓などで様々問題が増えてきています。
お墓の承継問題や古いお墓の撤去・墓じまいなどの事例が多くなり、
様々な供養や埋葬方法が増えています。
お墓引っ越しコンシェルジュが、
供養や風習、納骨方法、日本の風習などを
難しく解説をするのではなく、解りやすい説明を致します。
少しでも納得してもらえたら幸いです。
本日は、「眞應殿」を紹介します。
眞應殿は、搬送式納骨堂となり格調高い参拝ブースです。
1つひとつが区切られているため、プライベートな空間で静かに故人を偲ぶことができます。
また、室内の納骨堂の特長である天候に関わらずお参りができ、
草取りなどのお掃除の心配もありません。
JR川崎駅から徒歩6分、京急川崎駅から徒歩3分という
好立地もオススメポイントです。
法事・葬儀・会食施設等を併設してあり、建物は安心の耐震設計です。
最新の納骨施設ですが、
開創750年の風格が漂う川崎「曹洞宗 瑞龍山 宗三寺」が事業主なのでしっかりと供養されます。
宗教・宗派・国籍は問われませんので、どなたでも納骨できます。
これからも、お墓引っ越しコンシェルジュは、
改葬(お墓の引っ越し・お墓の移動・墓石の移し)・
古いお墓の撤去・墓じまいなどの相談や困り事のお手伝いを致します。
また、遺品整理やお墓参りの同行、お墓の掃除などのお手伝いも受け付けております。
今後は、様々な供養方法や納骨施設の情報などを公開していきます。
https://www.ohaka-hikkoshi-kaisou.com
2016年01月07日 21:45
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
七草粥 人日の節句 五節句
- カテゴリ: 五節句
お墓引っ越しコンシェルジュです。
最近は、終活という言葉が世間に認知されてきていますが、
超高齢社会の中、相続や介護・医療などの問題はさらに深刻になってきています。
そして、実家のお墓や親戚の田舎のお墓などで様々問題が増えてきています。
お墓の承継問題や古いお墓の撤去・墓じまいなどの事例が多くなり、
様々な供養や埋葬方法が増えています。
お墓引っ越しコンシェルジュが、
供養や風習、納骨方法、日本の風習などを
難しく解説をするのではなく、解りやすい説明を致します。
少しでも納得してもらえたら幸いです。
2016年1月7日は人日の節句(じんじつのせっく)です。
五節句の一番目となり、別名で七草の節句ともいいます。
人日とは古来中国に由来するものです。
古代中国では正月一日から、
「鶏、狗、猪、羊、牛、馬、人、穀」の順に獣畜の占いを立て、
七日になって人の占いを始めたということで、人日となりました。
人日の節句では、春の七草をお粥にして食べるのが一般的です。
その年の豊作や無病息災を願い、新年のお屠蘇(おとそ)や御節(おせち)などで
弱っている胃を休めるためと云われています。
この七草粥は、宮廷では平安時代には食されていて、室町時代の汁物が原型ともされています。
そして、江戸時代ごろに庶民へ広まったと云われています。
春の七草は地方によって全く異なりますが、一般的な七草を紹介します。
セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロとなります。
ちなみに、スズナはカブで、スズシロはダイコンのことです。
地方によって七草の食材は色々と異なりますが、草や野菜をメインとするのが多いです。
全国の地方によって全く違いますので、その年によって変えてみるのも良いと思います。
古来日本では、七草粥は1月15日に食していましたが、
人日の節句を一緒にするためと七草だから7日になってきたと云われてもいます。
これからも、お墓引っ越しコンシェルジュは、
改葬(お墓の引っ越し・お墓の移動・墓石の移し)・
古いお墓の撤去・墓じまいなどの相談や困り事のお手伝いを致します。
また、遺品整理やお墓参りの同行、お墓の掃除などのお手伝いも受け付けております。
今後は、様々な供養方法や納骨施設の情報などを公開していきます。
https://www.ohaka-hikkoshi-kaisou.com
2016年01月06日 23:43
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
小寒 しょうかん 二十四節気
- カテゴリ: 暦注
-
お墓引っ越しコンシェルジュです。
最近は、終活という言葉が世間に認知されてきていますが、
超高齢社会の中、相続や介護・医療などの問題はさらに深刻になってきています。
そして、実家のお墓や親戚の田舎のお墓などで様々問題が増えてきています。
お墓の承継問題や古いお墓の撤去・墓じまいなどの事例が多くなり、
様々な供養や埋葬方法が増えています。
お墓引っ越しコンシェルジュが、
供養や風習、納骨方法、日本の風習などを
難しく解説をするのではなく、解りやすい説明を致します。
少しでも納得してもらえたら幸いです。
-
2016年の1月6日は「小寒(しょうかん)」となります。
小寒は、二十四節気の第23目です。
-
小寒から「寒の入り」と呼ばれて寒さが厳しくなり始め、
そして、大寒を含めた節分までの30日を「寒の内」と呼び、
暦の上で寒さが最も厳しくなる頃だと云われています。
-
また、この日から年賀はがきが終わり、寒中見舞いを出し始めます。
-
これからも、お墓引っ越しコンシェルジュは、
改葬(お墓の引っ越し・お墓の移動・墓石の移し)・
古いお墓の撤去・墓じまいなどの相談や困り事のお手伝いを致します。
また、遺品整理やお墓参りの同行、お墓の掃除などのお手伝いも受け付けております。
今後は、様々な供養方法や納骨施設の情報などを公開していきます。
https://www.ohaka-hikkoshi-kaisou.com
2016年01月05日 23:34
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時
大晦日
- カテゴリ: 年中行事 風習
お墓引っ越しコンシェルジュです。
最近は、終活という言葉が世間に認知されてきていますが、
超高齢社会の中、相続や介護・医療などの問題はさらに深刻になってきています。
そして、実家のお墓や親戚の田舎のお墓などで様々問題が増えてきています。
お墓の承継問題や古いお墓の撤去・墓じまいなどの事例が多くなり、
様々な供養や埋葬方法が増えています。
お墓引っ越しコンシェルジュが、
供養や風習、納骨方法、日本の風習などを
難しく解説をするのではなく、解りやすい説明を致します。
少しでも納得してもらえたら幸いです。
本日は、「大晦日」です。
大晦日「おおみそか」は、1年の最後の日です。
みそかは、「三十日」と書いて、月の30番目の日を呼ばれるようになり、
そのため、年の最後の三十日の日を「大晦日」と呼ばれています。
または、「大晦」おおつごもりとも呼ばれ、
晦(つごもり)とは、月が隠れる日のつきごもりが変化したもので、
どちらも毎月の末日を指します。
昔は、日没から日付が変わっていたので、
年神様が家に来られてご挨拶をするのは31日に行っていたそうです。
そのため、神社へ参賀する初詣(2年参り)はしていなく、
明治の中頃に国から真影を拝むように命じられたのが、今日の初詣の習慣となっています。
また、大晦日の食事として年越し蕎麦があります。
細く長く幸せに生きる長寿と、胃腸を綺麗にする食事から無病息災の願いが込められています。
ただし、その習わしは、関東に多く、
関西では、運につながるためうどんを食べるところもあります。
そして、除夜の鐘で締めくくります。
鐘を煩悩の数である108回打ち、煩悩を1つ1つ取り除いて、清らかな心で正月を迎える習わしがあります。
年を超えてから最後の鐘を叩きますう。
他には、有名な秋田県の「なまはげ」も大晦日の行事の一つです。
また、神社では、大晦日に1年の間に受けた罪や穢れを祓うために、
大祓い(おおはらい)が宮中や全国の神社で執り行われています。
そして、この夜に早く寝ると白髪になる、シワが寄るなどの迷信があります。
本来、
神社が年神様を迎え入れる大晦日で大祓いを行っていた日ですが、
仏教が広まったのと、様々な時代の変化で
除夜の鐘などで、お寺も大晦日に参拝される方が多くなりました。
これからも、お墓引っ越しコンシェルジュは、
改葬(お墓の引っ越し・お墓の移動・墓石の移し)・
古いお墓の撤去・墓じまいなどの相談や困り事のお手伝いを致します。
また、遺品整理やお墓参りの同行、お墓の掃除などのお手伝いも受け付けております。
今後は、様々な供養方法や納骨施設の情報などを公開していきます。
https://www.ohaka-hikkoshi-kaisou.com
2015年12月31日 23:51
お墓の引っ越しをお考えなら、「お墓引っ越しコンシェルジュ」へ任せてください!
- TEL:03-6451-7394 【受付時間】9時~17時